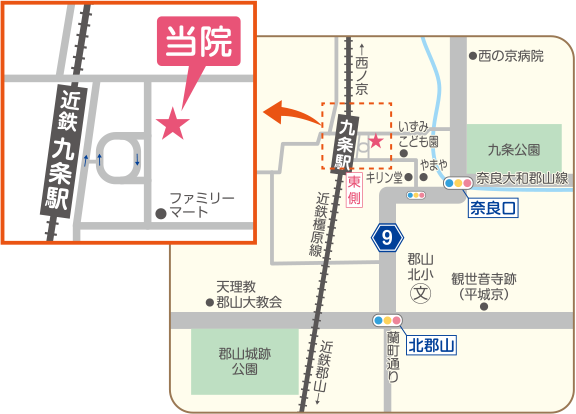小児アレルギー科について

アレルギーは体の色々なところに出現する可能性があります。どの部位に症状が出るかによって病名も変わり、花粉症(アレルギー性鼻炎)、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、じんま疹、食物アレルギーなど様々です。当院ではアレルギー専門医である院長が、アレルギー症状の診療を行いますので、子どもの症状でお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴った赤みやぶつぶつなど湿疹の症状が出て、よくなったり悪くなったりを慢性的に繰り返します。アトピー性皮膚炎は正しい外用薬の使い方やスキンケアをすると改善する場合も多いですが、中々よくならなかったり、一時的に改善しても直ぐに悪くなったりするので前向きな気持ちになれないこともあります。特に子どもの場合はお薬を塗って頂くのはご家族であることが多く、当院ではお薬を処方して終わりではなく、一緒に治療していく気持ちが重要であると考えています。
まずは子どもやご家族と治療目標を共有し、目標達成のためにはどのように治療していくのが適しているかを考えていこうと思います。治療は発疹が消失すると終わりではなく維持することも大切ですので、長いお付き合いになることもありますが、その時々に応じた治療を一緒に行っていきます。「治らないのに治療しても仕方がない」と諦めるのではなく、お悩みのことがあればお気軽にご相談ください。
気管支喘息
気管支喘息は発作的に起こる気道の狭窄によって、咳、ゼーゼーなどの症状を引き起こす疾患です。気圧の変化など軽微な変化でも発作が起こる場合もあり、中には運動すると症状が悪くなる方もいらっしゃいます。治療をせずにそのままにしていると、発作が繰り返され、気道の構造が変化し、気管支の壁が厚くなって気道が狭くなり、さらに発作が起こりやすくなってしまいます。これをリモデリングと言って、元には戻りにくい状態になり、症状のコントロールが難しくなってしまいます。
このため気管支喘息の治療は①今まさに息苦しいなどの症状が起きている時に治療する発作時の治療と②発作が起きないように安定させるための長期治療と分けて考える必要があります。どちらの治療も重要で同時併行で行うこともあります。気管支喘息は、とくに夜から明け方にかけて悪化することも多いので、子どもの自宅での様子をご家族にうかがいながら、その子に応じた治療を行っていきます。
気管支喘息は、日本では増加傾向にあり、乳幼児喘息など、低年齢化も進んでいるとみられています。喘息の治療は途中で中断しないことが非常に大切で、相談しながら一緒に治療を進めていきましょう。
食物アレルギー
食物アレルギーとは、ある特定の食物に対し、異常な免疫反応が起こってしまい、じんましんやかゆみなどの皮膚症状、咳、腹痛、嘔吐、下痢といった消化器症状などが現れるものです。以前は食べたものが原因で食物アレルギーが起こるとされていましたが、最近は皮膚から原因(アレルゲン)が侵入する(=経皮感作)ことによって発症すると言われています。このためまずは食物アレルギーの予防のために子どもたちの皮膚をすべすべの良い状態にしておくことが大切になってきます。
食物アレルギーは原因食物の特定が重要ですが、これは不必要な食物の除去を避けるためでもあります。一言に食物アレルギーといっても、新生児・乳児消化管アレルギーや口腔アレルギー症候群など様々な発症パターンがあります。これらの中には血液検査で分からないこともあり、検査が陰性であっても症状が出たり、検査が陽性であっても食べられるものも数多くあります。このためあらかじめ血液検査を行うことは不必要な除去に繋がる恐れがあるために推奨されておらず、原因特定にはご家族からの詳しい問診や食物経口負荷試験が重要となってきます。
当院では食物アレルギーと診断した場合でも、今後どのようにして原因食物を食べられるようにしていくかなど、治療方針をご家族と一緒に相談していきます。食物アレルギーがあるとご家族の不安も大きいかと思います。我々は子どもの成長には、食事が不安でいっぱいになることを避け、子どもやご家族が食事を一緒に楽しむことは非常に重要と考えています。当院が子育て支援になれるように努力していきますので、一緒に治療を行っていきましょう。
花粉症(アレルギー性鼻炎)
花粉症は、アレルギー性鼻炎のひとつです。アレルギー性鼻炎はハウスダストやダニなどが原因となって発症する「通年性アレルギー性鼻炎」と、スギやヒノキなどの花粉が原因となって発症する「季節性アレルギー性鼻炎」があり、後者のことを一般的に花粉症と呼びます。食物アレルギーと同様に血液検査で全てが分かるわけではなく、詳しい問診が診断には重要となります。例えば毎年1~5月に鼻炎症状がひどくなるのであれば、おそらく飛散するスギやヒノキ花粉症になります。ほかには初夏から秋にかけてのイネ科の植物、8~10月のブタクサなどが花粉症を引き起こす原因となります。
花粉症の症状がひどくなると、よく眠れなかったり、昼間の集中力が低下したりし、疲れやすい、いらいらする、といった生活面への悪影響が出てしまうほか、勉強に集中できないなど学業面に支障が出ることもあります。
花粉症の治療は花粉を浴びないこと(暴露されないこと)が最も重要とされています。外出時にはマスクやゴーグルをし、帰宅したら家の外で服をよく払ってから家の中に入ることがどんなお薬よりも大切になります。お薬は抗アレルギー薬や点鼻薬がありますが、眠気といった副作用で避けている方も多いかもしれません。一言に抗アレルギー薬といっても、種類は意外にも多くありますので、個々の患者さまに応じた治療薬を見つけていこうと思います。また治療開始は症状が出る前に行うことが重要ですので、花粉飛散前に受診頂けるとより効果的な治療が行えます。このほか、最近はスギ花粉症やダニアレルギーに対しては「舌下免疫療法」というアレルギーの根治療法が5歳以上の方にはなりますが適応になりました。当院でも舌下免疫療法を行うことが出来ますので是非ご相談ください。