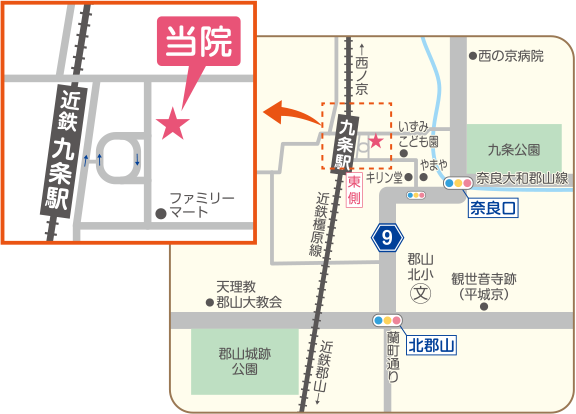小児の感染症について

子どもたちは様々な感染症(風邪)にかかります。発熱などの感冒症状があると、子ども自身もつらいのはもちろんですが、ご家族の方も不安になるかと思います。当院では子どものことを第一に考えながら、ご家族の育児・生活環境に合わせた治療を提案していきたいと考えています。
我々は小児医療の専門家ですが、その子自身の専門家はご家族です。このため当院ではご家族の「いつもと違う」いった気づき・不安は大切にしており、少しでも何かあればご相談頂ければ嬉しく思います。ご家族とともに子どもたちの健康を見守り、当院が子どもの健やかな成長の一助になれれば幸いです。
一般的な内容になりますが、子どもがかかりやすい感染症(風邪)の特徴について述べますので参考にしてください。
子どもがかかりやすい
感染症
感染症は主にウイルス感染、細菌感染、その他(真菌感染など)に分類されます。風邪のほとんどはウイルス感染によるものですが、特徴的な経過のウイルス感染・細菌感染がありますので、代表的な疾患をご紹介します。
溶連菌感染症
溶連菌といっても実は様々な群(A群~W群まで)が存在します。一般的に「溶連菌感染症」と呼ばれるものは「A群溶血性連鎖球菌」になります。通常は発熱と喉の痛みがあり、診察すると喉が真っ赤(火炎状といいます)になっています。その他、発疹や嘔気、腹痛が出現する時もありますが、咳や鼻汁が少ないといった特徴があります。
飛沫感染で伝播する細菌で、抗生剤治療が基本になります。治療をすると比較的早期に解熱する場合が多いですが、症状が改善しない場合はその薬に耐性のある溶連菌か、溶連菌以外の原因による咽頭炎の可能性もあるため、再度ご受診ください。
溶連菌は治療した後も腎臓や心臓に合併症を引き起こすことがありますので注意が必要です。溶連菌が治った後に血尿や浮腫が出現することがあれば必ずご相談ください。
アデノウイルス感染症
発熱、喉の痛み、目やにや眼が赤くなる咽頭結膜熱(プール熱)がよく知られていますが、アデノウイルスも様々な型が存在しますので実は症状も多彩です。アデノウイルスはどの型でも「ウイルス感染」になるので抗生剤は効果がありません。治療は症状に合わせた対症療法が主体になりますが、その子に応じた治療が必要ですのでご相談ください。
発熱や喉が痛くなるアデノウイルス咽頭炎、腹痛や下痢といったアデノウイルス腸炎でも、数日~1週間といったように症状はやや長くなる傾向にあるので、症状の悪化がないか注意する必要があります。またアデノウイルスは感染力が強いウイルスので、ご家族も手洗いはしっかり行うようにしてください。
突発性発疹
1歳前後に発症することが多いために初めての発熱として知られている疾患です。原因はヒトヘルペスウイルスによるウイルス感染ですが、特徴的な経過なので突発性発疹という名前がついています。症状は38℃~40℃程度の突然の発熱が3日間程度認め、解熱とともに腹部を中心に発疹が出現します。高熱が続くためにご家族もびっくりされる方が多く、また熱性けいれんを起こす場合も多いのでより不安になられるかと思います。突発性発疹の治療は脱水などに注意しながら経過を見ることになりますので、状態の悪化がないかご相談して頂ければ我々も安心です。20~40%程度は不顕性感染(感染していても症状が出ない)なので、気が付かないうちに罹患している子どももいるかと思います。
インフルエンザウイルス
感染症
インフルエンザは高熱や倦怠感を来たす疾患として有名です。インフルエンザも熱性けいれんを起こしやすいウイルスですし、高熱が出ますので発症するとご家族も不安になるかと思います。まずは予防の基本としてワクチンがあり、毎年10月前後からワクチン接種を開始しますのでホームページをチェック頂きたいと思います。万一インフルエンザウイルスに罹患した場合は抗ウイルス薬(タミフル®やイナビル®など)がありますが、いずれもウイルスの増殖を抑えるお薬になるので、使用後直ぐに症状が改善するわけではありません。病気を短縮させ早くに治す効果はあるので、当院では副作用も踏まえ、子ども一人一人に合わせてご家族と一緒に使用を考えていきます。
RSウイルス感染症・ヒトメタニューモウイルス感染症
RSウイルスとヒトメタニューモウイルスは全く別のウイルスですが、似たような症状を起こすので一緒に説明します。両疾患ともウイルス感染で、咳・鼻汁といった呼吸器症状と発熱を認めます。RSウイルスは生涯何度もかかるウイルス風邪ですが、初めての感染は2歳までにほぼ100%受けるとされています。この初めての感染が重要で、約30%程度は気管支炎や肺炎になることが報告されているので、赤ちゃんや小さい子どもは特に注意します。症状のピークもやや遅れる傾向にあり、最初は咳や鼻汁だけだったのに、数日後にどんどん熱が上がってくることも多いです。夜間に発熱することも多いので、ご自宅ではまずは眠れているかどうかや飲水(哺乳)出来ているかを見て頂くことが重要です。症状も長くなることも多いので、当院では診察、レントゲン・血液検査を行い、気管支炎や肺炎になっていないかなど注意深くみていきます。また最近は投与出来る方は限定的ですが、RSウイルスの予防薬なども出てきていますので情報提供していきます。
手足口病・ヘルパンギーナ
一般的には夏季に流行することが多いです。両疾患ともエンテロウイルスというウイルスが原因でかかる同じグループに属する風邪です。手足口病は発熱とともに口の中、手足、おしりに小さな水膨れのような発疹が出現します。39℃~40℃の発熱が出る場合もありますが、基本的には軽症で2日程度で解熱しますが、時に脳炎脳症など重症化する場合があるので注意が必要です。ヘルパンギーナは発熱とともに、発疹が口の中にのみ出来るものだと思ってください。手足口病と同様に基本的には軽症で早くに解熱しますが、熱性けいれんなども起こしやすいので注意が必要です( 熱性けいれんについても参照ください)。解熱した後に爪や手の皮がめくれてくることもあります。
クループ症候群
クループ症候群は疾患の名前ではなく、ウイルスなどにより声帯付近に炎症を起こしている状態の総称です。簡単に言えば、肺に炎症があるのが肺炎、気管支に炎症があるのが気管支炎といったように、声帯付近に炎症があることをクループ症候群と言います。声帯に炎症があるので犬が吠えるような咳、オットセイのような咳が出たり、声がかすれたり、熱も出ますが、やっかいなことに夜間に悪くなることが経験的には多い印象です。原因はウイルスや細菌など様々ですので、状態に応じた治療を行います。
ノロウイルス感染症
ウイルスの多くが胃腸風邪を起こす可能性があります。胃腸風邪を起こす代表的なウイルスがノロウイルスです。症状は発熱、嘔吐、下痢、腹痛がありますが、嘔吐の頻度が高い傾向にあるので、頻回の嘔吐があり驚かれるかと思います。特効薬などはないので、塩分や糖分の入っている水分を少量ずつ頻回に摂取頂き経過を見ることになります。ぐったりするなど症状の増悪がないか見ることが重要なので、普段と違った様子であればご相談ください。また非常に稀ですが、胃腸風邪が軽快する時期にけいれんを起こすことがあるので注意が必要です。感染は便や吐物からうつるので、処理する時は換気を行い使い捨ての手袋とマスクを装着し、次亜塩素酸ソーダを浸したペーパータオルなどで消毒してください。最後はビニール袋に入れて手袋とマスクと一緒に廃棄することも重要です。